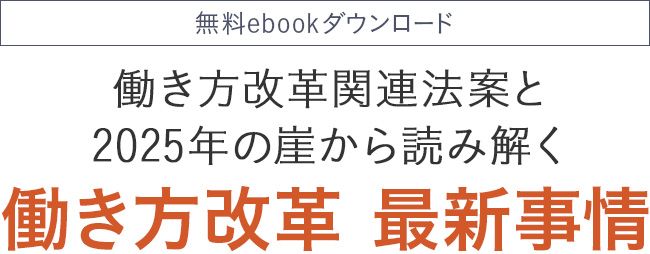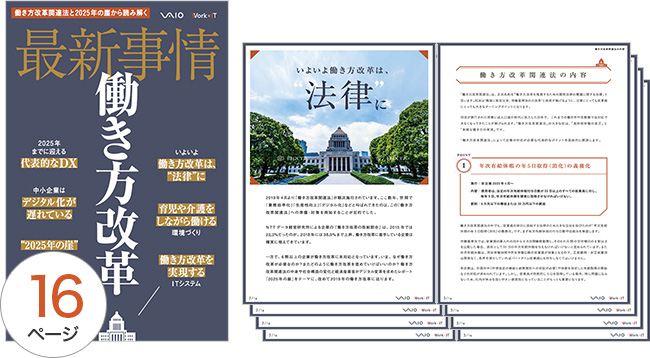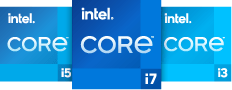2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」。「Work x IT」でもこれまでに同法に関連する働き方の変化やその対応について解説してきました。
「働き方改革関連法」は、労働基準法制定以来となる約70年ぶりの大改正と言われています。目的は労働人口減少への対策となる生産性向上と同時に、長時間労働が慢性化している働き方を変革することです。
今回は、「働き方改革関連法」でも肝となる「時間外労働の罰則付き上限規制」について解説します。「時間外労働の罰則付き上限規制」は、大企業には2019年4月1日に適用されていますが、中小企業は2020年の4月1日からです。
このタイミングで改めて「時間外労働の罰則付き上限規制」の内容を解説します。
目次
時間外労働とは? 法定外労働時間と残業の違いについて

「時間外労働の罰則付き上限規制」について解説する前に、時間外労働と残業について理解を深めておきましょう。まず「法定労働時間」と「所定労働時間」や休日について説明します。
労働基準法の第32条には労働時間について以下のように定められています。
“第三十二条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。”
(引用:電子政府の総合窓口「e-Gov」)
つまり1日8時間、1週40時間が法定労働時間です。この時間を超過すると「法定外労働時間」になります。時間外労働とは「法定外労働時間」のことを指します。
所定労働時間と残業について
法定労働時間とは別に各企業が就業規則で定めている労働時間を「所定労働時間」と言います。所定労働時間が1日8時間であれば、「所定労働時間=法定労働時間」となり、9時間を働いた場合は1時間の法定外労働時間が発生したことになります。
しかし、所定労働時間が7時間で8時間労働した場合は、「法定外労働時間」にはなりませんが、その企業内では「1時間残業」したという認識になるでしょう。しかし、法定外労働時間ではないのでその1時間に割増率は適用されません。
法定休日と所定休日について
休日については労働基準法の第35条に定められています。ここでは「法定休日」と「所定休日」と時間外労働の関係について説明します。
“第三十五条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。”
(引用:電子政府の総合窓口「e-Gov」)
労働基準法では、使用者は「1週1日、または4週4回の休日」を与えることが義務付けられています。この休日を「法定休日」と言います。また完全週給2日制を導入している企業では、「法定休日」の1日に加えて、「所定休日」が1日設けられていることになります。
法律上、「所定休日」に労働をした場合は、週40時間の超過分が法定外労働時間となります。また「法定休日」に労働した場合は、「休日労働」扱いとなり、法定外労働時間とは異なります(割増賃金に差が出ます)。
時間外労働の上限規制とは? 法律の改正点について
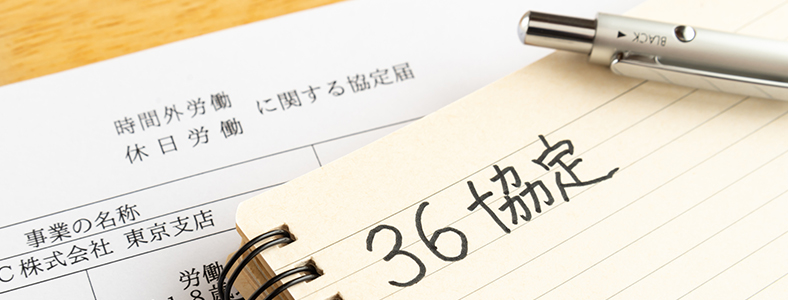
法定外労働時間について説明してきましたが、“法律上の残業の定義”をご理解いただけたのではないでしょうか。いよいよ本題に入ります。
企業は、従業員に対して自由に時間外労働をさせていいわけではありません。法定労働時間を超えて従業員に働いてもらうには、労働基準法第36条に基づく、労使協定を締結して、労働基準監督署に届出をしなくてはいけません。これがいわゆる「36協定」です。
しかし、「36協定」を締結した場合でも、時間外労働には上限が設けられています。これを超える時間外労働は違法とされるのです。下記をご確認ください。
| 36協定を締結した場合の時間外労働の上限 | ||
|---|---|---|
| 期間 | 一般の労働者 | 変形労働時間制の場合 |
| 1週間 | 15時間 | 14時間 |
| 2週間 | 27時間 | 25時間 |
| 4週間 | 43時間 | 40時間 |
| 1カ月 | 45時間 | 42時間 |
| 2カ月 | 81時間 | 75時間 |
| 3カ月 | 120時間 | 110時間 |
| 1年 | 360時間 | 320時間 |
長時間労働の温床だった特別条項付き36協定
このように時間外労働にも上限規制があったにも関わらず、日本で長時間労働の慢性化が問題視され、法改正で「時間外労働の罰則付き上限規制」が謳われているのはなぜでしょうか?
それは「特別条項付き36協定」の存在です。「特別条項付き36協定」は、臨時的かつ特別な事情が予想される場合に限り、1年の内6カ月に限り、前述の上限に関係なく時間外労働を行わせることが可能でした(労使間での締結が必要)。
1年に6カ月とはいえ、無制限に時間外労働が可能であることが、日本人の働きすぎの要因とされ、この度の法改正により改善されることになりました。
法改正で特別条項付き36協定にも上限規制が設けられる

では、2019年4月1日の法改正での変更点について解説します。「特別条項付き36協定」を締結した場合でも、下記の上限規制が設けられました。
【時間外労働の上限規制】
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2〜6カ月平均」それぞれ1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度
法改正により、細かく期間ごとに時間外労働の上限が定められたことで、企業は従業員の時間外労働をそれぞれの期間で超過しないように厳密に管理することが求められます。
違反した際の罰則
上記の上限を超えた場合には、事業主に対して6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
中小企業は2020年4月1日から適用。素早い対応が必要

「時間外労働の罰則付き上限規制」は、2019年4月1日から大企業には適用されていますが、猶予措置がとられていた中小企業は、2020年4月1日からとなります(建設業・運輸業など特定の業種は2024年4月1日から)。
「年次有給休暇義務化」「勤務間インターバル制度」に加えて、中小企業は就業規則の変更はもちろん、働き方そのものを変革していかなくてはいけません。まず必要なのは従業員の勤怠管理の徹底と労働時間の見える化です。
勤怠管理の徹底
勤怠管理は、「客観的で適正な方法で行わなければならない」とされています。現在ではクラウドでの勤怠管理の導入も進んでいますが、従業員が納得する手法かつ管理がしやすい勤怠管理を行う必要があります。
現状の労働時間を把握する
まずは従業員の労働時間を把握することが必要です。労働時間を把握して、分析することで、どの部署のどのような作業に時間がかかっているのか? またどの時期に時間外労働が多いのか? リソース配分は適正なのか? など自社の状態を知ることができます。
業務効率化・生産性向上の施策を講じる
労働時間の把握ができると、企業の業務プロセスの課題が見えてくるはずです。例えば、営業の移動時間を短縮するならば、リモートワークで業務効率化に期待ができるかもしれません。また経理業務もクラウドツールを導入すると一元管理が可能となり、効率化を図れるでしょう。業務効率化を目指すには、制度とデジタルツールの両面で検討するといいでしょう。
素早い対応が時代を生き抜く鍵となる
中小企業の働き方改革は待ったなしです。「時間外労働の罰則付き上限規制」につづき、2023年4月1日には月60時間超の時間外労働の割増賃金率が大企業と同じ50%となります。
「2025年の崖」など企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が世界から遅れていることも指摘されている日本。人口減少という社会構造の変化やテクノロジーの発展など、現在は大きな時代の節目と言えます。
働き方改革とデジタルトランスフォーメーション(DX)は同時並行で行っていく必要があります。経営陣は業務効率化を図りながらも、組織全体がデジタルネイティブになるように中長期のロードマップを作成し、組織改革が点ではなく線となるようにしなくてはいけません。
まずは法改正の対応をきっかけに組織を改めて見直してみてはいかがでしょうか。